ソフトウェアテストを学ぶうえで、**「欠陥管理(Defect Management)」**は非常に重要なテーマです。
テストでバグ(欠陥)を見つけること自体も大切ですが、「どう報告するか」が品質向上のカギを握っています。
今回はISTQB Foundation Level シラバス4.0の**Chapter 5.5「欠陥管理」**を、初心者にもわかりやすく解説します。
🔍 欠陥(Defect)とは?
まず基本から整理しましょう。
欠陥(Defect)とは、期待される結果と実際の結果の間に生じた不一致のこと。
たとえば:
-
ログイン画面で「正しいパスワード」を入力してもログインできない
→ 仕様どおりに動作していないため**欠陥(バグ)**です。
-
ボタンのラベルが設計書と異なる
→ 要件との不一致なので、これも欠陥にあたります。
ISTQBでは、欠陥を「期待値と実測値の差異(Deviation)」として定義しています。
🧭 なぜ欠陥報告書(Defect Report)が必要なのか?
テスト中に不具合を見つけたとき、「口頭で伝えればいいのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、口頭報告だけでは大きなリスクがあります。
理由①:他の関係者が正確に理解できない
テスターだけが不具合の再現手順を知っている状態では、開発者やマネージャーは判断できません。
欠陥報告書を書くことで、「どこで」「何をしたら」「どうなったか」を共有できます。
理由②:品質の可視化・追跡ができる
欠陥報告は単なる記録ではなく、製品品質を測る指標にもなります。
たとえば:
-
コーディングの欠陥が多い → 単体テストが不十分
-
要件誤解による欠陥が多い → 仕様レビューの改善が必要
このように、欠陥分析からプロセス改善のヒントを得ることができます。
理由③:継続的改善につながる
欠陥を体系的に記録・分析することで、次回のプロジェクトでは同じミスを防止できます。
たとえば、「要件定義の段階で見落としが多かった」とわかれば、次からはレビューを強化するなどの対策が可能です。
🧩 欠陥報告書に含めるべき項目(Defect Report Template)
ISTQBでは、**ISO/IEC 829(IEEE 829)**の国際標準をベースに、欠陥報告書に含めるべき項目を推奨しています。
ただし、プロジェクトや組織に応じてカスタマイズ可能です。
以下に代表的な項目を示します。
|
項目 |
内容 |
具体例 |
|---|---|---|
|
1. 一意のID |
欠陥を特定するための番号 |
DEF-00123 |
|
2. タイトル(概要) |
問題を一文で説明 |
「ログインボタンをクリックしても反応しない」 |
|
3. 発生日・報告日 |
いつ見つけたか |
2025-10-21 |
|
4. 報告者・所属・役割 |
誰が報告したか |
山田太郎(QAチーム) |
|
5. 対象オブジェクト・環境 |
どの環境で発生したか |
Android 14/アプリVer.1.2.0 |
|
6. 再現手順 |
ステップごとに説明 |
①ログイン画面を開く→②正しいID/PWを入力→③ボタンを押す |
|
7. 期待結果 |
本来どうなるべきか |
ホーム画面へ遷移する |
|
8. 実際の結果 |
実際の挙動 |
画面が固まって動作しない |
|
9. 添付資料 |
ログ・スクリーンショット等 |
「error_log.txt」「video_capture.mp4」など |
|
10. 重大度(Severity) |
システムへの影響度 |
High(機能が利用できない) |
|
11. 優先度(Priority) |
修正の緊急性 |
P1(即時対応が必要) |
|
12. ステータス |
現在の進捗 |
New / Open / Fixed / Closedなど |
|
13. 参照情報 |
関連するテストケースや仕様書 |
「TC_012_Login」「REQ_001_LoginFunction」など |
🧠 欠陥ライフサイクル(Defect Life Cycle)
欠陥は報告して終わりではありません。
実際には以下のようなライフサイクル(状態遷移)をたどります。
-
New(新規) – 発見直後の状態
-
Assigned(担当割当) – 開発者へ修正依頼
-
Open(対応中) – 修正作業が進行中
-
Resolved(修正完了) – 修正が完了した状態
-
Reopened(再発) – 再テストで再現した場合
-
Closed(クローズ) – 修正が確認され完了
このように、欠陥の状態を管理することで、進捗を可視化し、チーム全体の品質意識を高めることができます。
💡 欠陥データから得られる学び
欠陥報告書は単なる不具合記録ではなく、「品質向上の宝の山」です。
たとえば、100件の欠陥のうち:
-
70件が要件誤解によるもの
→ 要件レビューの改善が必要
-
20件が設計段階のミス
→ 設計ドキュメントレビューの強化
-
10件が単なる実装バグ
→ コーディング規約やコードレビューの見直し
このように、欠陥を分析することで「どの工程に問題が集中しているか」を特定し、**継続的改善(Continuous Improvement)**に活かせます。
🧾 まとめ
欠陥管理(Defect Management)は、テスト工程の中でも特に「品質を測る鏡」のような役割を果たします。
-
欠陥報告は「誰でも理解できる形で」文書化する
-
品質指標として分析し、プロセス改善につなげる
-
継続的改善のために、欠陥データを活用する
これらを実践することで、単なる「バグ修正作業」から一歩進んだ「品質文化」を築くことができます。



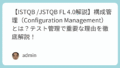
コメント